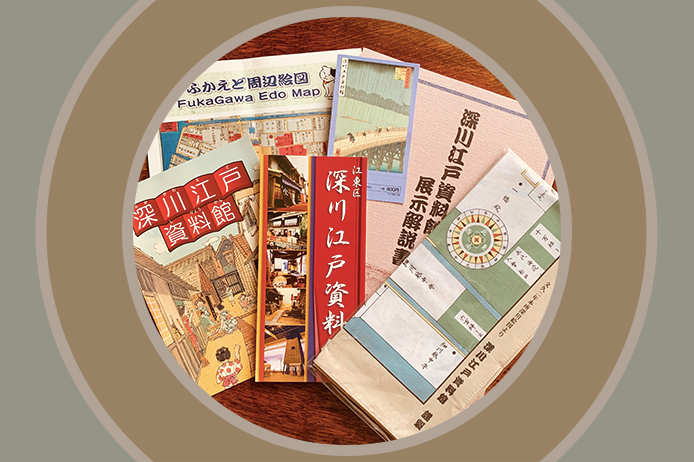目次
【東京気まま散歩その4】初めての清澄白川エリア|寺院と商店が集まる資料館通り
東京きまま散歩の第一弾では、江戸東京博物館の再訪の模様を書き連ねました。

同様の施設はあるのか気になるところです。
ネットで検索すると、清澄白川エリアに
深川江戸資料館という歴史体験施設がある事を知りました。

大江戸線や半蔵門線の「清澄白河駅」より徒歩3分。
深川江戸資料館は、資料館通り沿いにあります。
資料館通りは、多くの寺院が集まる清涼感溢れる空間。

【東京気まま散歩その4】清澄白川エリア|深川江戸資料館とは
深川江戸資料館は、公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団が運営。
江戸時代の深川の町を味わえる、体験型施設。

館内・個人入場料(2022年8月当時)
- 大人(高校生含む):400円
- 子供(小・中学生):50円
でした。
観覧券には、歌川広重の「大はしあたけの夕立」が印刷されていました。

深川ゆかりの浮世絵をチョイスされたのでしょうか。
深川江戸資料館は常設展示の他、企画展示もあります。
また、小劇場ホールも併設されており
落語などのイベントも楽しめるようです。
営業時間や、団体入場料など
詳しい情報は、オフィシャルサイトでご確認下さいね。
深川江戸資料館オフィシャルサイト
https://www.kcf.or.jp/fukagawa/
【東京気まま散歩その4】清澄白川エリア|深川江戸資料館内を体験
常設展示のエリアは、高い天井の吹き抜けフロア。
そこに広がる江戸時代の深川の町。
第11代将軍「徳川家斉(いえなり)」が大御所として権力を振るった
天保年間末期(1840年頃)を想定したものだそうです。
町並みは、深川佐賀町惣絵図(ふかがわさがちょうそうえず)を参考に再現されたとか。

案内役で看板猫?の実助(まめすけ)が、この資料館のキャラクター。
長屋の屋根でくつろぐ、実助の姿が目を惹きます。
 「探してみてなのニャ」
「探してみてなのニャ」

深川江戸資料館|町並みの作りについて
館内は昼夜の暗転があったり雷の演出があったりと、凝った空間となっています。
五感で江戸時代の雰囲気が楽しめるのが、テーマパーク的で面白いです。

休日は多めで、約350名前後とのこと。
また常設展示の写真撮影にSNSなど、ネット投稿も可能とお伺いしました。
是非とも、この体験型施設の楽しさを多くの方に知って頂きたいものです。
町並みの作りもとても興味深く、一気に江戸時代に惹き込まれます。
- お店が並ぶ表通りと、その先の町内への門
- 深川の運河を模した水辺に浮かぶ小舟、並ぶ船宿
- 火の見櫓(ひのみやぐら)や、屋台や水茶屋がある広場
- 庶民が暮らす長屋と井戸などの水回り、米屋の土蔵
と回遊出来る形なのですが
小物の演出も凝っていて、見飽きません。

お店や宿場、長屋も通路の動線が良く
色んなアングルから見る事が出来ました。
折角なので、見てきた一部について綴ってみたいと思います。
町内がよりリアルに見えるのは
住人の構成など、具体的に細かく設定しているからのようです。
この設定の詳細は、資料館でも販売中の「深川江戸資料館 展示解説書」に記載されています。

深川江戸資料館|表通りと町木戸
お店が並び、町の導入部としてみてもワクワクするエリアです。
干鰯魚〆粕(ほしかしめかす)・魚油(ぎょゆ)問屋の多田屋(ただや)

干鰯魚(ほしか)と〆粕(しめかす)は、鰯(いわし)から作られた高級肥料らしいです。
魚油は、行灯の燃料だったのでしょうかね。
八百屋の八百新(やおしん)

季節のお野菜がずらり。大根は「練馬大根」が陳列されているそうです。
八百屋さんの商品で、季節の移り変わりが感じられますよね。
舂米屋(つぎこめや)の上総屋(かずさや)

舂米屋(つぎこめや)は、玄米を精白して販売するお米屋さん。
日本人の主食といえば、お米。当時はどんなお味だったでしょうか。

実際に見てみると、もっと迫力がありますよ。
そしてその先には、門があります。
町木戸(まちきど)

町木戸は、町の防犯用に設けられた木製の門。
木戸というものが、門や出入り口の意味を持つようです。

木戸に纏わる、こぼれ話
個人的に面白いと思ったお話を書いてみたいと思います。
2020年3月、JR東日本が東京に「高輪ゲートウェイ駅」を開業しました。
しかし、なぜ「ゲートウェイ」というものが付くのか
賛否両論があったのは、記憶に新しいところです。

昔、東海道の江戸の玄関口として設けられた門が
高輪大木戸(たかなわおおきど)と呼ばれるものだったのです。
大きな江戸府内の門だったことから、大きい木戸=大木戸
だった訳ですね。

木戸という単語を覚えるきっかけにもなりました。
深川江戸資料館|水路「掘割(ほりわり)」
町木戸をくぐると、水路のエリアに出ます。
地面を掘削して作った水路が「掘割」と呼ばれるんですね。
深川の運河「油堀(あぶらほり)」を想定している
こちらの展示も、中々雰囲気抜群です。
走る小舟「猪牙船(しょきぶね)」

船宿所有の、人々の足代わりとなった小舟。
猪牙船の名には諸説あるようですが「猪の牙っぽい形」説は、なんとなく納得も。
船宿「相模屋(さがみや)」と「升田屋(ますだや)」
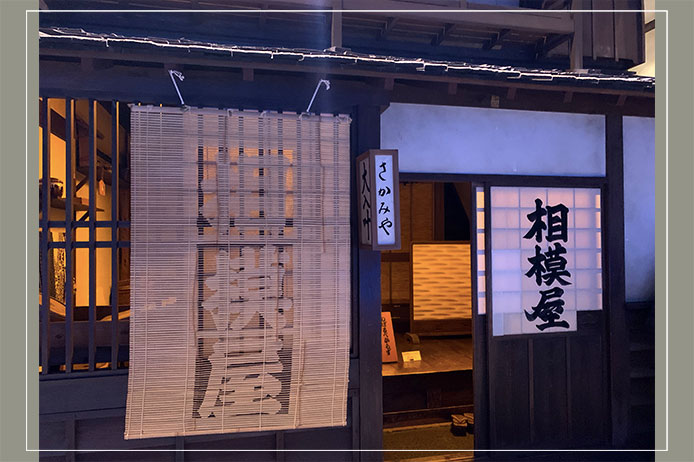
相模屋さん
簾にも屋号が入ってますね。

升田屋さん
佇まいの雰囲気の良さ。
こちらも、船宿のご主人・ご家族のキャラクター設定など
「深川江戸資料館 展示解説書」に書かれていて、面白いです。
深川江戸資料館|火の見櫓と屋台や水茶屋の広場
火の見櫓(ひのみやぐら)

「火事と喧嘩は江戸の花」と揶揄されるほど、火事の多かった江戸。
高さ約10mの櫓で番人が町を見守り、火事をいち早く知らせます。
天麩羅屋(てんぷらや)の屋台

「ちょい食べ」出来る、買い食いタイプの屋台。
串差し揚げの天ぷらに、江戸庶民は舌鼓を打ったようです。
水茶屋(みずちゃや)

江戸庶民の憩いの、今で言えばカフェといった趣。
お茶でホッと一息、世間話も弾みそうです。
深川江戸資料館|長屋、井戸や厠、舂米屋の土倉
長屋、船頭の家

写真が見切れてしまってますが
左端に、投網(とあみ)が見えます。
井戸や厠(かわや)、稲荷

写真手前には共同の井戸と、左手には厠=お手洗い。
奥にはお稲荷さんも。
舂米屋(つぎこめや)の土倉

深川佐賀町辺りは、お米の流通が盛んだったようですね。
集められた玄米も、ここならしっかり保管出来そうです。
【東京気まま散歩その4】清澄白川エリア|深川江戸資料館|まとめ
深川江戸資料館の常設展示のみ見回ったのですが
書き綴った以上に、展示内容は情報量が多く面白いです。
恥ずかしながら、大人になっても知らない事が多く
こういう、楽しみながら学べる施設は大変ありがたいものでした。
館内では、展示内容の解説書の他
グッズなどのお取り扱いもあります。
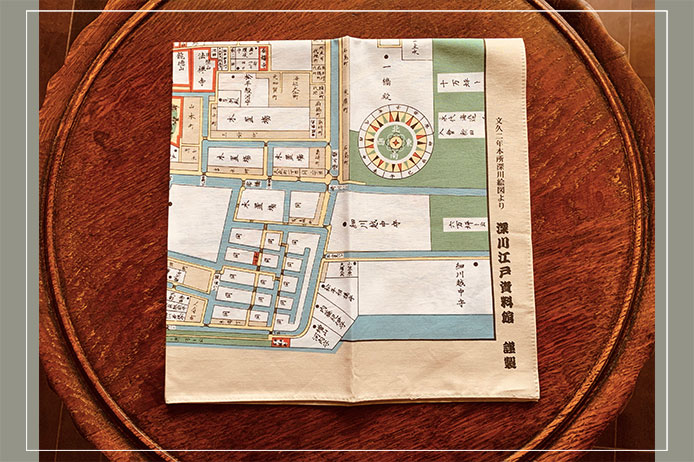
本所・深川絵図の切絵図ハンカチ、税込み500円。
訪れる前から欲しくて、今回購入。
歴史は地続きにある
そんな意味も感じられて良いですね。
運営に携わるご関係者の方々も、日々講じられている事でしょう。
知的好奇心をくすぐる、深川江戸資料館。
とても楽しい時間が過ごせたので、皆様も町木戸を潜ってお散歩を楽しんでみて下さい。
参考資料
「深川江戸資料館 展示解説書」
編集・発行:公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区深川江戸資料館